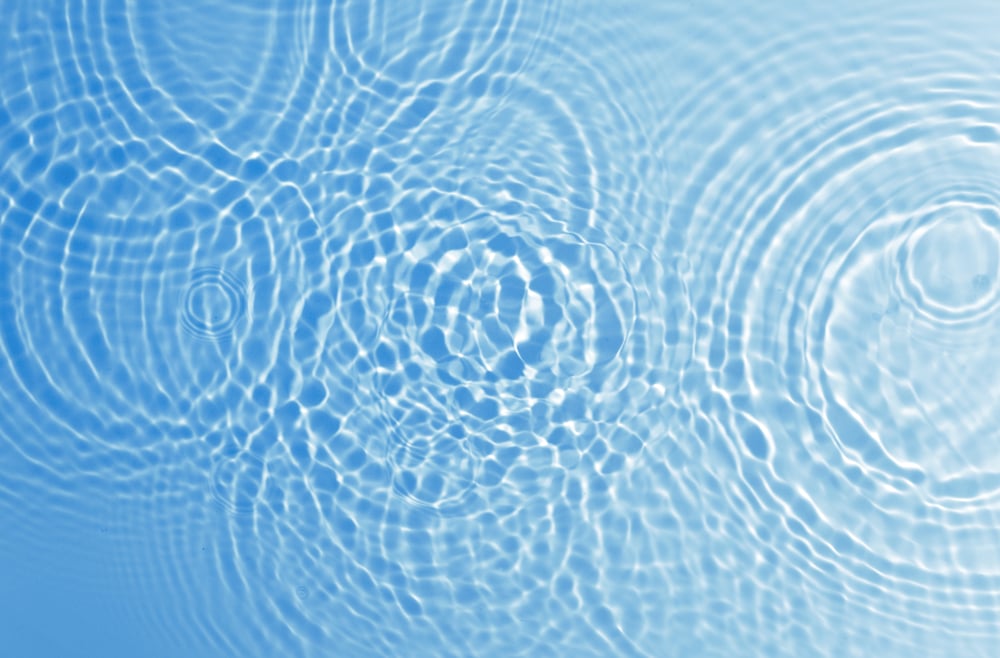「素(ス)」は最強

そもそも、「素」とはどのような状態であり、
如何なる理由で「素」は最強なのか。
「素」と人の能力、才能の発揮
創造性とはどのような関わりがあるのか。
どうすれば人は「素」に入ることができ、
「素」を妨げるものとは何なのか。
その答えを、今私たちは
「とほかみえみため」という言霊を通して
発見し、体感する好機に恵まれていますが、
振り返りますと、こういった思索と
その中で訪れる様々な気づきを
文字に落としていく作業は、
とても楽しいものでした。
日々のあれやこれやで
目まぐるしく過ぎてゆく日常の中で
この作業をしているときが
一番自分が「素」に還っていた時間
ではなかったかと思います。
これが何の役に立っていたのか
と聞かれますと、
それこそ素に還ってしまうといいますか
何とも答えられないところがあります。
ただ、「素」は「モト」とも読みますが、
生きていくうえで
何らかの「モト」(元・源)になって
くれたような気がするのは確かです。
実は深い「むちゃぶり」

以前、記事を執筆していたとき
久しぶりに「素」について
考えさせられたことがありました。
その記事の中で、
「むちゃぶり」という言葉を書くときに
「ぶり」をひらがなで書くか
「振り」と漢字で書くか
どちらにしようかと迷ったのですね。
それで、ひらがなと漢字のどちらが
主流なのだろう?と調べてみたときに
「むちゃぶり」という言葉の意味に
意外にも「素」という言葉を発見して
驚いてしまいました。
むちゃぶりとは、お笑いで用いられる「フリ」の一つ。
一般的なお笑いの形式としては、相手のキャラを考慮したうえで
それに沿った「フリ」を与えることになるが、
ここであえてそのキャラ設定を無視した対応困難な「フリ」を与え、
相手がそれに動揺して素を露呈してしまっているところを笑いに転化するのがむちゃぶりである。 (Wikipedia)
「むちゃぶり」って
実はこんなに深かったんですね。
「素を露呈して~」というのを読んで
また例の「素」をめぐる思索が
動き出してしまったわけです。
なるほど~。
ゼロ(素)になることで
マイナスを笑いというプラスに転化する、
「逆吉」そのものだな、とか
動揺は反転するチャンスであり、
反転するときは
必ずゼロを通過するとなると
やっぱり「素」ってポイントだな、
といったように。
古事記の最初の神を生む、言霊「ス」

ちょっと話が飛びますが、
言霊学では、
古事記で一番初めに登場する神
天之御中主神を言霊「ウ」として
この一者から、言霊「ア」(主体)と
「ワ」(客体)が生じるとして
天地創造の始まりを説いています。
そこで以前、七澤先生が朝のお話で
言霊「ウ」は、言霊「ス」から生まれる
というお話をしてくださったことがありました。
「ス」という言霊から、「ウ」が生まれてくるというんですかね、
母音が生まれてくる元の言霊が言霊学の中では説かれていて、
淡路(ア、ワ)島が、最初に島として生まれる前の「ウ」で、
また、「ウ」が生まれる前の「洲本(すもと)」の、
「ス」の元(もと)っていうようなですね。
器の教えで言うと、お酢ですね。
お酢を、結局、必ず膳の真ん中にのせるということを、
我々は、先生から聞いてきたんですけども、
それが、何故、酢なのかというと、「ス(静、素、州、巣)」の言霊であるし、
酢が、すべての日本でいうところの大山咋神(おおやまぐいのかみ)の発酵の働きですね。
お酢のものが、一番真ん中にあって、それから、ご飯とか味噌汁とか、おかずが置かれる。
それが、お膳の組み方なんだというかね。
あるいは、言葉の最後に、「ス」を付けるというのも、そういう大事な言葉の使い方ですね。
「ス」という最後に、そこで確実に終わるっていうんですかね。
始まりであり、終わりであるというようなものを、
「ス」の言霊ということを言っているんじゃないかと。
(はふりめく2018年12月6日)
ちょうど言霊「ス」について
考えていた朝このお話があったことに
とても驚いたので、よく覚えています。
「ス」ということに関して
大変示唆に富んでいる内容ですが、
皆さんはこのお話から、何を感じますか?
私は、「発酵」の働きを象徴する
お酢(ス)を膳の真ん中に乗せる
というお話が鮮烈でした。
私たちの生命を支える食、
とくに身体が喜ぶ食事をしようと思えば、
「発酵」は必ず
その中心に据えるべきものです。
たとえば、よい作物を作るには
よい土である必要がありますが、
よい土は、微生物の働きによる
発酵を取り入れることで実現します。
ひとたび和食に目をやれば、
醤油、みりん、味噌、漬物、
納豆、日本酒といった発酵食品が
その中心を担いますね。
こうした発酵食品文化こそ
ユネスコの無形文化財に和食が選ばれた
中心的な理由であったはずです。
土と和食の要(中心)ともいえる
発酵(酢)を膳の中心に据える慣習と
言霊「ス」が明かす言霊の中心点、
なるほど、と思います。
先祖と繋がる「ス」

ところで、こうした発酵の文化であったり
発酵したよい土(土地)を守ってきたのは
どんな方たちでしょうか。
そう、ご先祖様方ですね。
遺伝子や細胞レベルだけでなく
食や土地といったものを通しても、
私たちの命と日常は
ご先祖様に支えられているのです。
私たちを作る「素(モト)」である
食、土地、そしてご先祖様を
大切にしていきたいですね。
もちろん、それは素の集まりとしての
自分という存在を
大切にすることでもあります。
そして、冒頭のお話でいいますと、
「とほかみえみため」によって
「スッ」と落ち着いた感覚があるのは
ご先祖様の存在とあわせて、
そんな言霊「ス」の消息を深いところで
感じ取るからなのかもしれません。
「とほかみえみため」を唱えながら
ご先祖様、そして「ス」とともに歩んで
いきたいなと、あらためて思うわけです。
この記事を書いた人
浅子雄一郎
neten株式会社/ラボラトリオ株式会社研究員
早稲田大学教育学部卒。
ヴィパッサナー瞑想からマントラを使った瞑想など様々な瞑想法を経て、白川学館の門を叩く。
言霊の叡智を装置化したロゴストロンの信号で、それまでの瞑想の体感が一変。この体験に衝撃を受け、800年間宮中祭祀を司ってきた白川伯王家伝承の「おみち」を生涯実践することを心に決める。
祓い、鎮魂、言霊を実践しながら、自らが世界の人々と「おみち」との結び手となるべく、日々奮闘中。